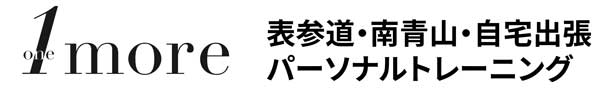筋力アップ目的でも、ダイエット目的でも、トレーナーに教わると必ずといってよいほど登場するのが「スクワット」。下半身トレーニングの王道であり、道具なしで行えます。初心者でも続けることで大きな効果を出せるのが、今から説明する「スクワット」です。
コロナウィスルの影響で自宅でテレワークしている方にも、おすすめのトレーニングです。今回は、スクワットの効果から、鍛えられる部位、正しいフォームの解説、11種類のバリエーションや、スタンス・深さの違いまで、専門家が詳しく解説していきます。
【専門家解説】スクワットの効果|なぜスクワットがトレーニングとして優れているか?
スクワットの効果① 体脂肪燃焼効果が高い
体脂肪を落とす目的で運動するなら、活動代謝量の高いトレーニングであるスクワットは最たるトレーニングの一つです。スクワットは全身の筋肉の60%を占めるといわれる下半身ほとんどの筋群に強い刺激を与え、それだけでなく体幹の筋肉も運動されています。
体脂肪の燃焼に働きかけたいのなら、運動される筋肉の総量が大きい方が活動代謝量が高くなり、体脂肪が燃えやすくなるため、腹筋運動を10回行うよりも、正しいフォームでスクワットを10回行う方が効率的です。
スクワットの効果② 全身の筋肉を同時に鍛えることができる
スクワットで動員される筋肉の数は、あらゆるトレーニング種目の中でもナンバーワンと言われています。
太ももやお尻など下半身を鍛えるイメージがありますが、正しいフォームでスクワットすることで、背中や腹筋など体幹の筋肉まで刺激されます。スクワット1つでほぼ全身の筋肉を同時に鍛えることができるので、効率面で優れたトレーニングです。
スクワットの効果③ 太ももが引き締まり美脚になる
「スクワットをすると太ももが太くなる」というイメージを持つ女性は多いかもしれませんが、それは間違ったフォームでスクワットを行なっているか、高い負荷をかけてストイックに鍛えている場合です。
スクワットは美脚づくりに必要な、すべての筋肉に刺激を与えられる優れたトレーニングです。また、脚の内側に効くスクワット、お尻に効くスクワットなど、その方の目的に応じたバリエーションも揃っています。
脚の間に隙間が入るような美脚を目指したい方はぜひチャレンジしてみましょう。
スクワットの効果④ ヒップアップ効果で、脚が長く見えるようになる
脚を長く見せたいならスクワットでお尻やももの裏を引き締めましょう。お尻と脚にはっきりと境目が見えるくらいヒップアップすると、後ろから見て脚がスラッと長く伸びている印象を与えることができます。
スクワットはヒップアップ目的の方にも効果的です。スクワットは股関節を深く曲げ伸ばしするトレーニングですので、股関節の動きに反応するお尻の筋肉(臀筋)やももの裏(ハムストリングス)が鍛えられ、お尻をリフトアップさせてくれます。
スクワットの効果⑤ 姿勢が良くなる
スクワットを正しいフォームで行うことで、姿勢保持に重要な脊柱起立筋をはじめ、骨盤姿勢を支える腸腰筋群や臀筋群(お尻の筋肉)が働きますので、柔軟性を取り戻し、骨盤を本来の位置に改善させる効果もあります。
姿勢の衰えは、猫背や背中痛、ぽっこりお腹の原因となります。長年の座業で背中の痛みに悩んでいる方、猫背姿勢でカラダが動かしづらい方など、姿勢が原因の不調で悩んでいる方は、スクワットを取り入れることをオススメします。
スクワットの効果⑥ 心肺機能が向上する
心肺機能を鍛える方法は有酸素運動だけではありません。スクワットなど体を上下させる運動は、ジョギングや水泳のように心肺機能を強化することにも適しています。
重力に逆らいながら体を上下に動かすような運動は、座ったり寝た状態での運動と比べて心肺機能の負担が大きく、短時間で心拍数や血圧を上昇させます。
また、下半身の筋肉を使う運動は、心臓から遠い位置の筋肉まで重力に逆らって素早く血液の循環をさせねばならず、筋ポンプ作用や心臓血管系の働きが活発になります。
スクワットは体を上下させる運動であり、かつ、下半身の筋肉を使う運動ですので、健康状態に留意して行えば、効率よく心肺機能を向上させる優れたトレーニングと言えます。
【専門家解説】スクワットで鍛えられる筋肉部位
スクワットで鍛えられる部位① 大腿四頭筋&ハンストリングス
大腿四頭筋は、太ももの前側を覆う4つの筋肉の総称です。主に膝を伸ばすときに働き、人体の中で最も大きくて強い筋肉であり、ジャンプ力を向上させるには欠かせない筋肉です。
※大腿四頭筋 → 大腿直筋・中間広筋・外側広筋・内側広筋の総称
ハムストリングスは、太ももの裏側にある3つの筋肉の総称です。膝を曲げるときや股関節を伸ばすときに働きます。走るときの推進力に影響する筋肉で、ダッシュやランニング時にストライドを広げてスピードに乗るには、強いハムストリングスが必要です。
※ハムストリングス → 大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋の総称
スクワットで鍛えられる部位② 大臀筋・中臀筋
大臀筋は、お尻の筋肉の中で最も大きい筋肉で、椅子から立ち上がるときなど股関節が伸びるときに働きます。ヒップアップには欠かせませんが、それ以上に直立歩行を可能にしているのが大臀筋なので、生涯に渡って鍛えていきたい筋肉です。
中臀筋は、お尻の横側から大臀筋の深部に伸びる筋肉です。脚を開脚したり、歩行や運動時に骨盤がグラグラしないようバランスを取るのに働きます。スポーツ選手なら誰しも動作の安定性を向上させたいでしょうが、それならば中臀筋強化は欠かせません。
スクワットで鍛えられる部位③ ヒラメ筋&腓腹筋
ヒラメ筋と腓腹筋両方で、ふくらはぎの筋肉として認知されています。かかとを持ち上げるときに働きます。第二の心臓とも呼ばれ下半身の血液を心臓へ循環させる役割をしているので、生涯に渡って衰えないよう鍛えていきたい筋肉です。
ふくらはぎの筋肉は足首の動きに反応するので、自重程度の負荷ならば通常のスクワットよりは、足首が動くジャンピング・スクワットやスプリットスタンス・スクワットの方が高い刺激を与えられるでしょう。
スクワットで鍛えられる部位④ 脊柱起立筋
正確には脊柱起立筋群と呼ばれ、脊柱の背面側にある筋群の総称です。背骨の動きに連動して姿勢を支える筋肉です。姿勢の改善や体幹力の向上には欠かせません。
スクワットは本来脊柱起立筋をメインに鍛えるトレーニングではありませんが、正しいフォームでスクワットをしている間、この脊柱起立筋が姿勢の安定や保持のために働くので強化につながります。
脊柱起立筋 → 腸肋筋・最長筋・棘筋の総称
スクワットで鍛えられる部位⑤ 体幹部深層筋群
体幹深層筋群とは、胴体の奥にあり姿勢保持に関わる筋肉の総称です。この筋群はスクワット時に腹圧を高めて姿勢を安定させ、下半身と上半身との筋肉の連携に重要な役割を果たしています。
スクワットでこの筋群を効果的に鍛えていくには、頭の先から足裏まで正しいフォームを守って行うこと。バーベルやダンベルで負荷を徐々に高めていけば、下半身の強化と一緒に体幹深層筋群も強くさせることが可能です。
体幹深層筋群 → 腹横筋・内腹斜筋・横隔膜・腰方形筋・回旋筋・多裂筋などの総称
【専門家解説】スクワットの正しいフォームのやり方を解説
スクワットの手順(ノーマルスタンス・スクワットで解説)
- 両足の幅は肩幅より少し広めが目安。つま先は少し外側に向けておく。
- 背筋をしっかりと伸ばす。バーを背負っている場合はさらに、肩甲骨を寄せて胸を張り、顔はやや上方へ向けておく。
- 【スタート】まずお尻を後ろに突き出す動作から始め、息を吸いながら、ゆっくりしゃがんで胸を下げていく。
(心持ちかかとに体重を乗せておくこと)
- 太ももが床と平行になるくらいまで下げたら、グッお腹で息を止める。
- 足裏で地面を押し上げ、胸を元の姿勢まで起こしていく。
- 元の姿勢まで起こしたら、フーッと息を吐き出す。【フィニッシュ】
- 終了まで3〜6を繰り返す。その間、2の状態を常にキープすること。
まずは、正しいフォームで20回を目安にチャレンジしてみましょう。スクワットには様々なバリエーション種目がありますが、姿勢や呼吸の使い方、動きの要領はおおそよ共通しています。そのため、ノーマルスタンス・スクワットのフォームを習得しましょう。
【専門家解説】こんなフォームは要注意。よくあるスクワットの間違ったフォーム
間違ったフォーム1.背中が丸まっている
スクワットで絶対にやってはいけないこと、それは背中を丸めたままスクワットをすることです。腰や背中にストレスがかかり腰椎椎間板ヘルニアを引き起こしやすくなります。
下半身のフォームや動きばかりに気を取られずに、まずは背をできる限りまっすぐに伸ばした姿勢を作ってからスクワットを始めましょう。
ポイント : 胸を張るように肩甲骨同士をキュッと軽く寄せておこう!
間違ったフォーム2.足元や床を見てスクワットをしている
真下を向いてスクワットをすると首(頸椎)が曲がり、背骨の連鎖反応で胸や腰も曲りやすくなり、背筋をしっかり伸ばす姿勢が難しくなります。スクワット中は足元や床を見てはいけません。目線は常に前方(やや上方)です。
目線を常に前に置いておけば、上体を下げた時は自然と顎が上がり首が伸びるので、背筋もまっすぐに伸ばしやすくなります。
ポイント : 動作中、目線は常に前方(やや上方)を見ておく!
間違ったフォーム3.上半身が前に倒れすぎている
上半身を前に倒しすぎると、背中を丸めてスクワットするパターン同様に、腰や背中にストレスがかかり腰椎椎間板ヘルニアを起こしやすくなります。特に反り腰の女性に多く見られるパターンです。
スクワットのスタート時は胸を起こしてその姿勢をキープして行うように意識しましょう。ただし、胸を起こすことに一生懸命になり腰を強く反るのは禁物です。
ポイント : 胸を起こした姿勢をキープして、下げていく!
間違ったフォーム4.つま先よりも膝を前に出して行っている
スクワットを「膝の屈伸運動」だとイメージしていませんか?膝がつま先よりも前に出したスクワットを続けると膝関節を痛めやすくなります。必ず正しいフォームに修正しましょう。
スクワットを「股関節の屈伸運動」とイメージしましょう。椅子に座る動きと同じように、お尻を後ろに引くように上体を下げて行きます。そうすれば自然とかかと側に体重が乗り、膝が前に出過ぎることを防げます。
ポイント : 膝ではなく、股関節でスクワットをする!
間違ったフォーム5.かかとに体重が乗っていない
かかとに体重が乗っていない状態でスクワットを行うと、お尻やももの裏の筋肉がうまく働かず、太もも前(大腿四頭筋)ばかりに負荷が集中してしまうスクワットになります。
かかとに体重が乗らない原因として、「間違ったフォーム4.」のように、つま先よりも膝を前に出して行っているケース、または、足首の筋肉が硬くて上手にしゃがみ込めないという原因も考えられます。
柔軟性が問題なら、ストレッチで柔軟性の改善を優先させることが根本的解決につながりますが、早くスクワットをしたい!という方は、かかとの下にプレートや板を敷き、その上にかかとを置くようにすると、かかとが浮く問題をクリアできます。
ポイント : かかとに体重が乗らないなら、膝の位置や柔軟性をチェックしてみよう
間違ったフォーム6.ガニ股や内股になっている
スクワットの動作中は、常に膝とつま先は同じ方向でいること。よくある間違いのケースとして、足幅が狭すぎるとガニ股になりやすく、逆に広すぎると内股になりやすくなります。膝の向きが安定する足幅(スタンス)を見つけましょう。
足幅の問題ではなく、下半身の筋肉が硬い場合や、O脚X脚の骨格異常から、どう頑張っても膝が外側や内側に逃げてしまう方もいるでしょう。この場合はフォームが確立するまで無理は禁物。柔軟性や筋力のバランスを改善することが先決です。
ポイント : 膝は常につま先と同じ方向でいるように!
【専門家解説】正しいフォームを身につけたら、スクワットの効果を上げるコツを学ぼう!
効果を上げるコツ1. 回数よりも、フォームの質で効かせる
スクワットの効果を早く出したいなら、第一に「正しいフォームで続ける」こと。スクワットの正しいフォームのやり方の手順を守り、効かせたい筋肉への刺激を感じ、その刺激を最後まで抜かないように続けることで、効果を出すための負荷が高まります。
回数はその人の目的にもよりますが、自分が決めた回数を正しいフォームで最後まで続けてみましょう。20回が問題なくできるようになったらコツ2・コツ3を参考にしてみてください。
効果を上げるコツ2. 足裏でグッと地面を押し上げる
スクワットは膝を伸ばす力で立ち上がろうとしてはいけません。膝の力で立ち上がろうとすると大腿四頭筋ばかりが働いてしまいます。足裏の使い方を身につけることで、脚部の筋肉をバランス良く、そして、強く発揮させることができます。
上体が下がったところで息を止め、足裏でグッと地面を強く押し、その押し上げる力で元の姿勢まで上体を戻すことを意識してスクワットしてみましょう。この時重要なのは、足裏のかかと側を特に使って押し上げることです。
かかと側に力を加えると、お尻や太もも裏側の筋肉が反応しやすくなります。このコツを生かすとスクワット効果が倍増します。
効果を上げるコツ3. 可動域を広げる
浅いスクワットよりも、深くしゃがみ込むスクワットの方が負荷が高まります。可動域を広げるほど運動自体はキツくなりますが、運動量や筋肉にかかる負荷が増すのでスクワット効果が上がります。
また、お尻やももの裏の筋肉は、可動域が広がるほどに刺激が高まります。ヒップアップ効果を狙っている方は、スクワットの深さを太ももが床に平行になるまで下げるパラレル・スクワットを目標に取り組んでみましょう。
効果を上げるコツ4. 負荷を少しずつ高めていく
スクワットの効果を上げる最も良い方法は、負荷を少しづつ高めていくことです。2週間後も、1ヶ月後も、いつも同じやり方で行わず、筋肉が負荷に慣れすぎないように、少しづつ階段を登るように、負荷のレベルを上げていきましょう。
負荷を高める手段は、単にバーベルやダンベルの重量をどんどん上げていくことだけではありません。回数を1回づつ増やす、可動域を数センチ深くするなどの手段も筋肉にとっては新鮮な刺激であり、スクワットの効果を上げるキッカケとなるでしょう。
【負荷を高める手段例】
- 回数を増やす
- セット数を増やす
- 可動域を大きくしていく
- 器具の重量を増やす
- セット間の休憩時間(インターバル)を短くしていく
【専門家解説】スクワットのバリエーションを紹介
ノーマルスタンス・スクワット(通常のスクワット)
足幅を肩幅より少し広め目に開いて行う、一般的なスクワットです。太ももの表裏、内外、臀部まで、脚部全体をバランス良く鍛えることができます。まずはこのスクワットをマスターするところから始めてみましょう。
ワイドスタンス・スクワット
ノーマルスタンス・スクワットよりも足幅を広く取って行うバリエーションで、太ももの内側(内転筋)により大きな負荷をかけることができます。
前傾姿勢を抑えやすいスクワットなので、股関節が硬い人や、体幹が弱い初心者には比較的取り組みやすいバリエーションです。内ももを引き締め、逆に太ももの外側は鍛えすぎたくないという女性にはワイドスタンスが最適です。
ブルガリアンスクワット(シングルレッグスクワット)
足幅を前後に開き、後ろ足を椅子や台に乗せて行うスクワットです。前足側に負荷がかかります。膝を前に出しすぎず正しいフォームで行うと、前足側のヒップに強い刺激を与えることができ、女性にも人気のバリエーションです。
お尻を後ろに引いてから下げ始め、前脚の太ももが床と平行になるまで深く下げると、お尻の筋肉に効きやすくなります。上半身は決してのけ反らないないように、まっすぐ立てておくか、心持ち前傾姿勢にしておきましょう。
ジャンピング・スクワット
スクワット動作のフィニッシュ時でジャンプをするバリエーションです。上体を下げた状態から、その反動を利用して高くジャンプ動作を行います。
膝や足関節に大きな負荷がかかる種目なので、負荷や回数、フォームに十分気をつけて行う必要があります。
スプリットスタンス・スクワット
両足を前後に開いた姿勢で行うバリエーションです。上半身を垂直に立てて行うパターンと、やや前傾にして前脚側に体重を乗せて行うパターンがあります。前者は両足に満遍なく負荷がかかり、後者は前脚側の臀筋やハムストリングに良く効きます。
シシー・スクワット(シッシー・スクワット)
大腿四頭筋に良く効くスクワットバリエーション。どちらかの手でテーブルや椅子の背につかまり、肩幅のスタンスで立ちます。膝から肩まで一直線になる姿勢を保ちながら、膝を曲げて上半身を後傾させ、十分に下げたところで元の姿勢まで戻します。
スクワットバリエーションの中で、唯一、膝関節の動きのみで行うスクワットです。大腿四頭筋の膝付近に強いテンションがかかるので、膝に問題を抱えている人は他のバリエーションに変更するか、フォームに十分気をつけて行いましょう。
ダンベル・スクワット
両手にダンベルを持って、ノーマルスタンス・スクワットを行います。自体重でのスクワットから負荷を変化させたい人、また、上半身の柔軟性が硬くバーベルスクワットが困難な人は、ダンベルスクワットがおすすめです。
両手にダンベルを持つとバランスが取りにくい場合は、1個のダンベルまたはケトルベルを両脚の間で持って行ってみましょう。
ダンベル・ワイドスクワット
1個のダンベル、またはケトルベルを両手で持ち、ワイドスタンス・スクワットを行います。股関節が柔らかくダンベルが床についてしまう場合は、両脚それぞれに台をセットして足位置を上げることでこの問題は解決します。
バーベル・バックスクワット
バーベルを肩の後ろにかついで行うスクワットのことです。自体重やダンベル使用のスクワットよりも難易度は上がりますが、下半身だけでなく体幹(特に脊柱起立筋)の強化に優れています。
ワイドスタンスにすれば、太ももの内側(内側広筋・内転筋群)を効かせやすくなります。
バーベル・フロントスクワット
バックスクワットより、体幹がより垂直に近い姿勢になるので、大腿四頭筋への刺激が大きいスクワットです。また、姿勢の保持が難しいので、体幹の強いキープ力が求められるバリエーションです。
肩にバーを乗せて腕組みをするように肘を曲げて、交差した手をバーの上から抑える方法と肘が床と平行になるまで上げてオーバーハンドグリップでバーを握る方法があります。
オーバーヘッド・スクワット
バーを天井へむけてまっすぐ掲げたままスクワット動作を行います。バーベル・バックスクワットよりもさらに肩の柔軟性やバランス能力も求められる難易度が高いバリエーションです。
全身のバランス能力や体幹力のパフォーマンスアップを狙う目的にも適したバリエーションです。スクワットに必要な肩や胸まわりの柔軟性を獲得するのにも最適です。
【専門家解説】スクワットのスタンスによって効果が変わる
ノーマルスタンス
両脚を肩幅または肩幅より広めに開き、つま先をやや外側に開くスタンスです。
脚部全体をバランス良く鍛えられる効果があります。
ワイドスタンス
ノーマルスタンスよりもさらに広いスタンス。膝から下(スネの骨)が床と垂直になる程度の足幅が目安です。
ノーマルスタンスに比べ、外側広筋の刺激が弱まり、逆に内側広筋・内転筋の刺激が入りやすくなります。太ももの内側を引き締めたり、鍛えたい人に効果的なスタンスです。
スプリットスタンス
両脚を前後に開いたスタンス。足幅は狭くも広くもせず腰幅程度が目安です。
後ろ脚側の大腿四頭筋や腸腰筋群など、股関節の伸筋がほど良くストレッチされるので、脚部を鍛えるだけでなく、股関節周辺の柔軟性アップにも効果的です。
ブルガリアンスタンス
スプリットスタンスのように前後に開き、後ろ足を椅子や台に乗せたスタンスです。
スプリットスタンスよりも前脚側の筋肉により強い刺激を与える効果があります。
【専門家解説】スクワットの深さ(可動域)はどこまでが適性か? | 運動目的や身体状況に合わせて設定しよう
深さレベル1「パーシャル・スクワット」
股関節と膝をわずかに屈曲させる程度にしゃがみこむスクワット。(股関節と膝が約150°)
非常に重いウェイトにチャレンジすることができます。大腿四頭筋に強い刺激を与えたい時や、脊柱起立筋の固定力改善に効果的です。
深さレベル2「クォーター・スクワット」
フルスクワットの4分の1程度の深さまでしゃがみこむスクワット。(股関節と膝が約120°)
深さレベル3「ハーフ・スクワット」
パラレル・スクワットとクォーター・スクワットの中間程度の深さまでしゃがみこむスクワット。(股関節と膝が約90°)
ハーフ・スクワットあたりからお尻の筋肉(臀筋)の関与も大きくなってきます。ヒップアップ目的の方には、深さレベル3以降のスクワットをおすすめします。
深さレベル4「パラレル・スクワット」
太もも上部が床と平行になるまでの深さまでしゃがみこむスクワット。
最も一般的なスクワットで、「スクワットの正しいやり方を解説」での手順は、このパラレル・スクワットのことです。
大腿四頭筋から、臀部までバランス良く鍛えることができます。
深さレベル5「フルボトム・スクワット」
太もも上部が床と平行よりも深くなるまでしゃがみこむスクワット。
体幹の固定力や柔軟性が求められる、最も難易度が高いスクワットです。